浅漬は自作の白だしで
冷蔵庫にある◯◯だし 皆さんは冷蔵庫に、市販の「◯◯だし」とか「◯◯たれ」とか「◯◯つゆ」とかってどのくらいお持ちですか?そのたぐいの物って、味が「甘すぎる」とか、逆に「濃すぎてしょっぱいな」とか、やっぱり流通保存する前提で作られているからか「風味が足りない」とか…そんな味への不満もさることながら…
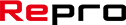 キッチンでは、お料理と
キッチンでは、お料理と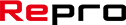 にまつわる、いろいろなお話を開発チームが書きとめていきます。
お料理のちょっとしたコツから、
にまつわる、いろいろなお話を開発チームが書きとめていきます。
お料理のちょっとしたコツから、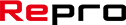 で作るステキなレシピや、知っていると便利なTipsも。
で作るステキなレシピや、知っていると便利なTipsも。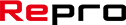 と関係ある情報も、ない情報も、何しろキッチンでちょっと役に立つ楽しい情報をお届けします。
と関係ある情報も、ない情報も、何しろキッチンでちょっと役に立つ楽しい情報をお届けします。
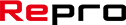 の使い方とレシピと食材と。
の使い方とレシピと食材と。冷蔵庫にある◯◯だし 皆さんは冷蔵庫に、市販の「◯◯だし」とか「◯◯たれ」とか「◯◯つゆ」とかってどのくらいお持ちですか?そのたぐいの物って、味が「甘すぎる」とか、逆に「濃すぎてしょっぱいな」とか、やっぱり流通保存する前提で作られているからか「風味が足りない」とか…そんな味への不満もさることながら…
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。そして、皆さんもそろそろおせち・お雑煮にも飽きてきた頃合いかと。新年早々カミングアウトしますが、個人的には「お餅」にさして情熱を持っている方ではありません。お正月以外は、ほとんど「お餅」のことを忘れていて、年末に「そろそろお雑煮の準備…
湯せんタイプの低温調理器 低温調理器と言うと、例えば「A●OVA」とか「B●NIQ」とか、円筒状の、いわゆる「湯せんタイプ」を連想しますよね?内蔵するスクリューで真水(お湯)をかくはんしながら、これまた内蔵したシーズヒーター(つまりは電熱線)で加熱し、一定の温度を保つというタイプで、最も一般的です…
本かえしのその後 前回はそばの「本かえし」を作りました。詳細はこちらをごらんください。 それから1週間。あの時は「1日だけ開放系で寝かせる」と言いましたが、なんとか頑張って3日間は開放系を維持しました。変化はと言うと、まず一晩開放系で寝かせると、部屋に漂っている出来立ての時の少し鼻にツンとくるしょ…
そろそろ年末年始の準備を始める季節になりました。今年こそは年越しそばも手作りしたいと思うも、そばを打つ勇気も場所も技術もなく…そこでせめて「そばつゆ」(正確には「かえし」と「だし」)だけでも手作りしてみようと思い立ち、ネットでそばつゆの作り方を検索していたら、このヒゲタしょうゆさんのサイトに行き当…
よく和食のプロたちは「素人でも一番簡単に失敗なく作れる魚料理は煮魚」と言ったりします。確かに魚の切り身を買ってきたり、丸ごと煮られる小さいサイズであれば、そもそも「魚をおろす」という、慣れない方にはややハードルの高い作業がありませんしね。ただ不安な点も。「美味しくきれいに煮られるのかな?」というの…
このレシピをお手本に本格的なリゾットを作ってみる リゾットって簡単そうで、作ってみると「おじや」みたいなモッタリ感が出たり、意外に難しかったりします。そこで今回はこのレシピを参考にしてみようと。 この伊勢丹新宿店の柬理美宏シェフのレシピって以前から素敵だなあと思っていたんですよね。 リゾットをアル…
1年前のコラム記事をnoteに移植したら 約1年前に「餃子の焼き方について考える(1)亀戸ぎょうざ編」というコラムを公式サイトに書いたのですが、それを今頃になって「note」にも移植しました。 この中には以下の一文も。 「餃子を焼く最適温度は180℃時を同じくして、noteに公開されている、焼き餃…
オーディエンスタイプとプレーヤータイプ どうも人間には2つのタイプがあるようで。コンサートに行ったり、アルバム(最近はサブスクですが)を聞いたりすると、「ああ、良い曲だなあ。また聞きに行きたいなあ」と思う良きオーディエンスタイプと、「ああ、良い曲だなあ。自分もあんな風に弾いてみたい(歌ってみたい)…
「鶏肉のカシューナッツ炒め」は伝統中華だと思ってたけど… たいていの中華料理屋さんにはある人気定番メニューの一つ「鶏肉のカシューナッツ炒め(腰果鶏丁)」。でもそれは純粋に中国で生まれたレシピではなく、アメリカに移民した中国人が生み出した「born in America」な一品のようです。 そう言わ…
酒のアテになるなら… いつも「酒のアテ」になるようなものしか作らないので、お菓子作りに全く興味がわかない人生でした。甘い物が嫌いなわけではありません。たまに美味しいケーキや和菓子を食べれば感動するし、飲み過ぎた後にはアルコール分解のためにブドウ糖を体が欲するのか、無性に甘い物が食べたくもなります。…
Wakiyaさんに続いて「名店の中華風蒸し鶏」の第2回目はこちらです。Wakiyaさんとは色々な意味で対照的な「蒸し鶏」かと。 不動のスペシャリテ「鶏煮込みそば」で有名な六本木の名店 夜の街 六本木に静かに佇む中華の名店「香妃園」。 言わずもがな、不動のスペシャリテ「特製とり煮込そば」があまりに有…
前菜には蒸し鶏を食べたい 「さあ今日は中華でビールを!」と気合が入った日には、それが町中華であれ、高級中華料理店であれ、メニューに「蒸し鶏」があれば、まずは前菜に注文してしまうんですね。それはもう儀式の如く。我ながら鶏肉がよほど好きなんですかね…それにしても中華料理って、チャーシューというと「叉焼…